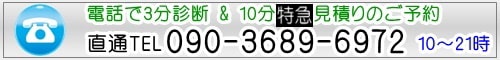データ復旧率・復元率とは何?
某データ復旧業者さんのサイトに「特徴:復旧率95%以上」として掲載されているページを見かけます。
ちなみに、世界全業者平均の復旧率=[分母が持ち込まれた件数]で[分子が復旧できた件数]だと仮定しますと65%だそうです。(民間のデータ復旧業者の一部、日本データ復旧協会のホームページによる情報であり日本国の運営ではありません)
当店へのお問い合わせで「復旧率がホームページに掲載されていませんが何%ですか?」という問い合わせを多く頂きます。
なので、この点について解説させて頂きます。
本意ではありませんが、2024年1月よりデータ復旧率とデータ再現率という項目で数値を掲載する事に変更しました。
データ復旧業界として統一された定義は一切ございません。
また、[データ復旧率]と[データ復元率]の違いもありません。
[データ再現率]は日本データ復旧協会さんだけ?!が使われている意味不明の言葉です。
各社様のホームページには、何の根拠も無い数字を勝手に(根拠となる定義なし)掲載されていたり、復旧作業の結果報告書に記載されています。
数値の根拠を明確に記載されていれば宜しいのですが、ただ単純に数値だけを掲載されたサイトもよく見かけますので、大切なデータが消失して不安な気持ちになっている方につけ込んで混乱させているようです。
このような詐欺まがいの表記は、同業者として決して許される事ではない。と考えます。
データ再現率
関東の某大手データ復旧専門業者(A社)のホームページには[データ再現率]という変な用語が掲載されています。
当店にも問い合わせが増えていますので、一応説明させて頂きます。
[データ再現率]とはいったい何?(A社の定義)
その業者様のホームページには、[データ再現性100%]の定義が記載されています。
データ再現率=調査後報告データと納品後データが同じである事。とされています。
[調査]=[復旧作業]であればデータ再現率=アルバイトの方が作業しても当然100%ですね!
また、[復旧できたデータ量]=[調査後提示データ量]が同じである事。とされていますが、これも当然100%ですね!
全国の多くの健全なデータ復旧業者が、某業者は[悪〇業者]だと認識されている業者が広告している[データ復旧率95%以上]に対抗している広告記事が、たぶんこの[データ再現率]なのでしょう。
[データ再現率]とはいったい何?
[データ復旧率]とはいったい何?
どちらも訳の解らない定義ですね!
そもそも[調査後に報告済みファイル数]と[復旧後に再現できたファイル数]が異なる事自体があり得ない事なのです。何を持って[調査]と言うのでしょうか??? もし[調査]が完了しているのであれば[データ復旧作業]は既に完了しています。
つまり、100%同じに決まっているのです。
データ復旧の工程
1:初期診断で物理障害か論理障害を切り分け。
2:論理障害と判定した場合、論理復旧を行い、結果からリストを作成して提示します。
3:軽度の物理障害と判定した場合、障害ディスク全体のイメージデータを回収、そのイメージデータから論理復旧を行い、リストを作成して提示します。
4:重度の物理障害と判定した場合、障害ディスクを開封(HDDの場合は蓋を開け事。USBメモリーの場合はメモリーICを基盤から取り外す事)し、不良部品を交換したり、イメージデータを回収し、その後に論理復旧を行います。
成功率とは?
[データ復旧サービス]では、成功率を記載しても何の意味もありません。そもそも定義がありませんから・・・
掲載する事は良い事?悪い事?
サイトに掲載する場合はその根拠(分母と分子)を明確に表記すべきだと思います。
根拠のない数値は掲載すべきではありません。
某大手業者では「復旧率は95パーセント」等と掲載されています。
しかし、ちなみにHDDの場合の業界平均復旧率は「65%前後(2024年現在)」が正しいようです。
もし90%以上の数値を掲載されていれば【嘘・偽り】、もしくは【重度障害のHDDは受け付けていない業者】でしょう。そもそもその数値の根拠が掲載されていませんから何の意味もありません。(但し2023年末現在はそうでしたが2024年11月現在は昔の話となりました。つまり技術の進歩で常識は変わりました。)
例えば「メーカー名がSeagate」の「型番ST2000DM001(容量2TBモデル)」や「型番ST3000DM001(容量3TB)」等のモデルは自然故障による寿命もダントツ早く、ヘッドクラッシュ(破損したヘッドがプラッターに接触して傷付ける事)したら復旧ができませんでしたが、これも昔の話です。
重度障害時に於ける結果報告できる数値は
- 納品可能なファイル数
- 納品可能なデータ量
- 正常と判定されたファイル数とデータ量とフォルダ名とファイル名と拡張子
- 破損ファイルと判定されたファイル数とデータ量とフォルダ名とファイル名と拡張子
- グレーゾーンと判定されたファイル数とデータ量とフォルダ名とファイル名と拡張子
HDDの復旧率は98%以上
2024年11月現在、HDDのデータ復元率は98%以上です。
この数値は案件ベースで、分母が復旧を依頼された数、分子が復旧でき納品できた数です。
不良が多く復元率に問題があるといわれ、受付されていないモデルSeagate製の1TB以上のモデル(例えばST2000DM001やST2000DM003やST3000DM001等)も含まれています。
ヘッド破損で異音を発している状態も含みます。
以上はHDDの場合であり、SSDやメモリーメディアは復元率は悪いです。年々益々悪化傾向です。
社内に限り統計をとれる数値は?
計算するには分母と分子が必要ですが、以下の統計は取れるでしょう。
- 診断を申し込まれた件数
- 復旧をご注文された件数
- 障害メディア(回収元)から回収できた容量
- 回収できたセクター数(物理最小単位)
- 回収できたファイル数
- フォルダ名が復元できた数
- 上記、ファイル数
- 整合性が正しいファイル数
- 正常に開けたファイル数
- 静止画像の場合は、[ブレビュー]の[特大アイコン]で100%の面積が復元できた枚数
- 静止画像の場合、[プレビュー]の[中アイコン]が表示できた枚数
- 静止画像の場合、[プレビュー]の[小アイコン]が表示できた枚数
- 動画の場合、スタートアイコンに静止画像アイコンが表示されたファイル数
- 動画の場合、先頭から終わりまで正常に閲覧できたファイル数
- Officeファイルの場合、修復要求のメッセージが表示されずに開けたファイル数
- コンテンツ内のデータに文字化けがなく色の復元や計算式の復元ができたファイル数
- 納品ファイル数
- 納品データ容量
復旧率・復元率・成功率のまとめ
以上の通り、どの数値を分母にし、どの数値を分子にするかにより、復旧率は大きく異なるのです。
つまり、統計数値が正しかったとしても、何の意味もない、比較するのは無意味な数値なのです。
[パソコンデータ福岡]では、復旧率は掲載しない方針です。
また、各ユーザー様への結果報告書には、ハードディスク(HDD)の場合、計算式の分母はHDD全体の容量やセクター数、分子は障害HDDから作業用HDDへコピーできた容量やセクター数で表現するようにしています。
故障前のファイル数がいくつだったのかは誰も判りませんから・・・。
メモリーの場合は、HDDのような計算はほぼ不可能です。メーカーが表示している容量も適当な数値です。
USBメモリーの場合、ケースに記載されている型番シールも剥がれていたり、摩擦で文字が消えている物が多いのです。型番を金属部に刻印されてるのはSONYだけでしょう。